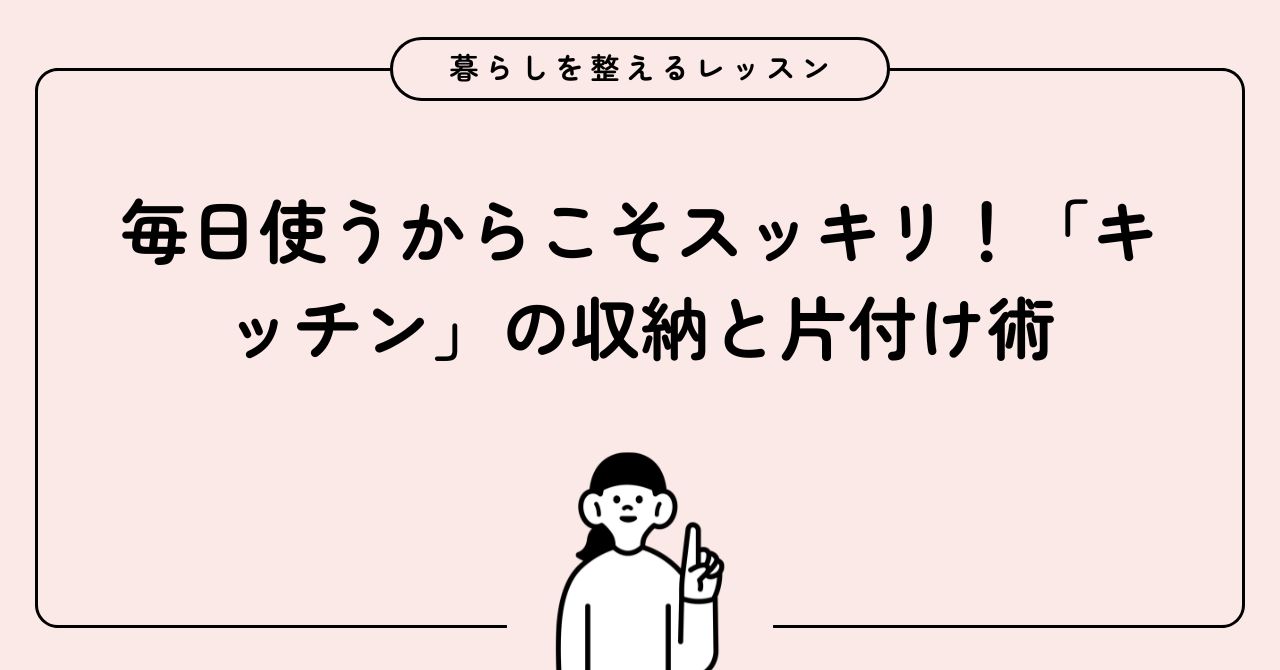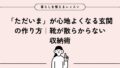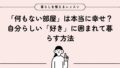キッチンは、毎日使う場所だからこそ、
気づけばモノで溢れ、ごちゃごちゃになりがちです。
「同じような調味料がいくつも出てきた…」
「食器棚がパンパンで、奥のお皿が取れない…」
そんな小さなストレスを感じていませんか?
料理はもっと楽しく、クリエイティブな時間になるはず。
そのためには、使いやすく、見ていて気持ちのいいキッチン環境が欠かせません。
この記事では、そんな理想のキッチンを実現するための、
具体的な片付け術を3つのステップでご紹介します。
難しいテクニックは必要ありません。
誰でも今日から実践できる簡単な方法で、料理がはかどり、
キレイをキープできる「散らからない仕組み」を一緒に作っていきましょう。
なぜキッチンはすぐに散らかる?よくある3つの原因

キッチンの片付けが特に難しいと感じるのには、ちゃんとした理由があります。
「うちだけ散らかっているのかも…」なんて思う必要はありません。
多くのご家庭が、以下の3つの原因によって、キッチンの散らかりに悩んでいます。
キッチンがごちゃつく3大原因
- モノの種類が多すぎる:
調理器具、食器、食材、調味料など、多種多様なアイテムが集まる場所。 - 使用頻度がバラバラ:
毎日使う一軍と、年に一度しか使わない二軍が混在している。 - ストック管理が難しい:
食品の在庫が把握しきれず、無駄買いや賞味期限切れが起こりやすい。
これらの原因を知ることで、解決の糸口が見えてきます。
ステップ1:まずは全部出す!「中身」の要・不要を仕分ける
キッチンの片付けも、基本は他の場所と同じです。
まずは、収納スペースから「全部出す(全出し)」ことから始めましょう。
成功のコツ!
一度に全部出すと途方に暮れてしまうので、
「今日はカトラリーの引き出しだけ」
というように、小さな範囲から始めるのがおすすめです。
中身をすべて出したら、以下の基準で「要るモノ」と「不要なモノ」を仕分けていきます。
「不要なモノ」を見極める4つの基準
- 賞味期限切れの食材・調味料
- 1年以上使っていない調理器具
- 欠けた食器や傷んだ道具
- 重複しているアイテム(ピーラー、おたま等)
この作業でモノの総量を減らすことが、使いやすいキッチンへの最も重要なステップです。
ステップ2:調理がはかどる「ゾーニング収納」の基本
モノの厳選が終わったら、次は「どこに何を収納するか」を決めていきます。
ここで役立つのが、作業動線に沿って収納場所を決める「ゾーニング」という考え方です。
調理中の無駄な動きをなくし、劇的に効率を上げるための基本なので、ぜひ取り入れてみてください。
キッチンを3つのゾーンに分けて考えよう
- シンクゾーン(洗う):
ザル、ボウル、包丁、まな板、洗剤など - コンロゾーン(火にかける):
フライパン、鍋、おたま、油、よく使う調味料など - 調理ゾーン(切る・混ぜる):
菜箸、計量カップ、ラップ、保存容器など
このように、使う場所の近くに使うモノを収納するだけで、「あっちこっち動き回る」という無駄がなくなり、料理がスムーズに進みます。
ステップ3:劇的に使いやすくなる!収納の3つのコツ
ゾーニングで大まかな配置が決まったら、最後は、より使いやすくするための具体的な収納テクニックです。
プロも実践している、簡単なのに効果絶大な3つのコツをご紹介します。
コツ① 「立てて収納」で、取り出しやすく
フライパンやお皿を重ねて収納すると、下にあるものが取り出しにくく、ストレスの原因になります。
ファイルボックスや専用のスタンドを使って、「立てて収納」することを意識してみましょう。
まるで本棚から本を取り出すように、使いたいものを片手でサッと取り出せるようになります。
コツ② 透明な容器で「見える化」する
それでは残量が分かりにくく、在庫管理がうまくいきません。
これらを透明な保存容器(クリアケース)に移し替えるだけで、中身と残量が一目瞭然になります。
見た目に統一感が出て美しく、何より「同じものをまた買ってしまった」という無駄買いを防ぐことができます。
コツ③ 使用頻度で「高さを変える」
収納の鉄則は、「よく使うモノほど、一番取り出しやすい場所に置く」ことです。
キッチンで最も取り出しやすい「ゴールデンゾーン(目線から腰の高さ)」には、毎日使う一軍のお茶碗やお皿を配置しましょう。
逆に、年に数回しか使わないお客様用の食器や、季節もののアイテム(土鍋など)は、吊戸棚の上段やシンク下の奥など、少し取り出しにくい場所に収納します。
このルールを守るだけで、日々の動作が驚くほどスムーズになります。
まとめ:毎日の「リセット習慣」でキレイなキッチンをキープ

今回は、毎日使うキッチンをスッキリ快適にするための、片付けと収納のコツをご紹介しました。
理想のキッチンを作る3ステップ
- まず「全部出し」で不要なモノを手放し、モノの総量を減らす。
- 動線を意識した「ゾーニング」で、モノの定位置を決める。
- 「立てる」「見える化」「高さを変える」の3つのコツで、収納を最適化する。
一度この仕組みを作ってしまえば、キッチンは格段に使いやすくなるはずです。
そして、この状態をキープするために最も大切なのが、毎日の簡単な「リセット習慣」です。
難しく考える必要はありません。例えば、一日の終わりに、寝る前の5分間だけ、
「調理台の上には何も置かない状態にする」
「シンクの中を空にする」
というルールを決めて実践するだけです。
この簡単なリセットを毎日続けることで、汚れも散らかりも蓄積せず、いつでも気持ちよく使えるキッチンを維持できます。
ぜひ、できることから一つずつ試して、料理がもっと楽しくなるキッチンを手に入れてくださいね。