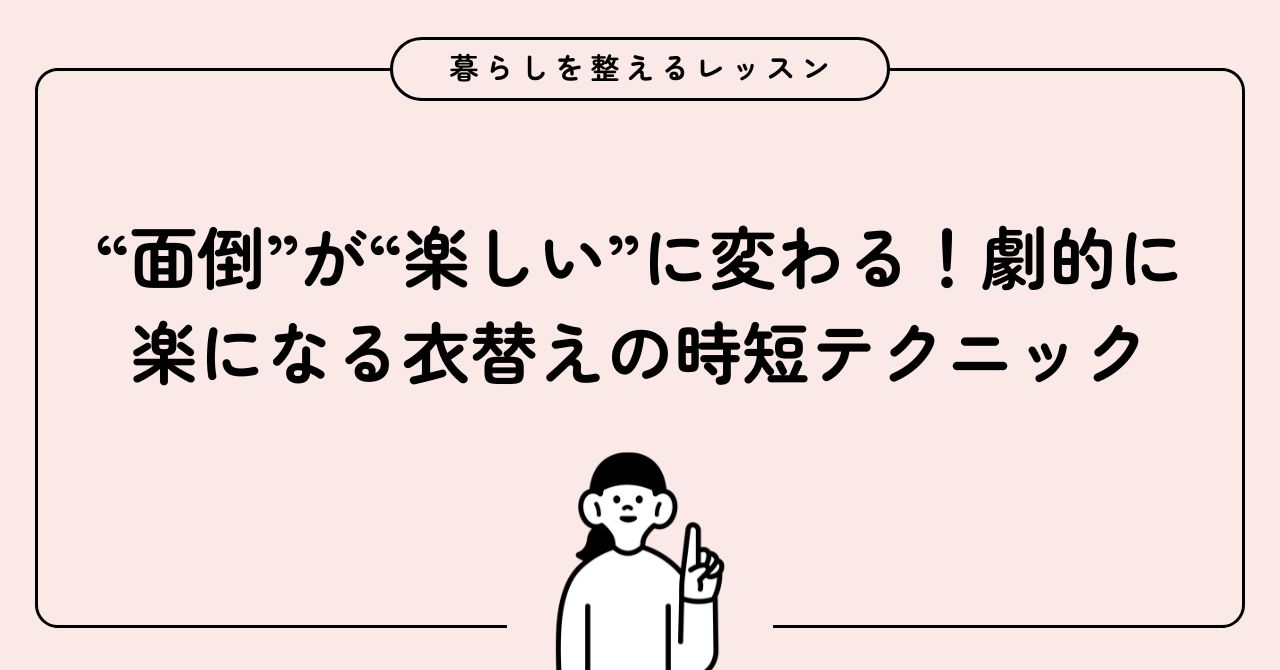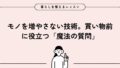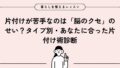春と秋、季節の変わり目にやってくる、あの恒例行事「衣替え」。
まるで一大プロジェクトのようにのしかかる衣替え。
その“面倒くささ”の正体を、まずは一緒に分解してみましょう。
なぜ衣替えはこんなに面倒?心が折れる3つの理由

かつての私も、衣替えと聞いただけで気分が沈んでいました。
その理由は、大きく分けて3つあったように思います。
理由1:「全部出す」という圧倒的な絶望感
クローゼットの奥から重い収納ケースを引っ張り出し、ベッドや床の上に服の山を築き上げる…。この物理的な労力と、その後の部屋の散らかり具合に圧倒されて、始める前から心が折れてしまうのです。
理由2:「いる・いらない」の判断が、もはや脳トレ
「この服、今シーズンは一度も着なかったな…。でも高かったし…」「来年になったら、また着たい気分になるかも…」こうした“かもしれない”という未来への期待や、“もったいない”という過去への執着が、判断を鈍らせます。
一枚一枚の服と向き合うことは、想像以上にエネルギーを消耗する作業です。
理由3:「しまう前のケア」という見えない手間
洗濯やクリーニング、防虫剤の準備など…。
こうした見えない手間の多さが、「衣替え=面倒」というイメージを決定づけているのです。
面倒が楽しみに変わる!衣替え“新常識”5つのステップ
もう、憂鬱な衣替えは終わりにしましょう!
ここでは、従来の常識を覆す、心理的にも物理的にもハードルがぐっと低い「新しい衣替えの方法」を5つのステップでご紹介します。
STEP 1「全部出し」はしない!“今シーズンの服をしまう”から始める
最初の革命です。オフシーズンの服を出すのではなく、「今、着ている服」をしまうことから始めましょう。
クローゼットにかかっている服の中から、「もう着ないな」という夏服(または冬服)だけを対象にするのです。
この方法なら、部屋が服の山で埋め尽くされることはなく、隙間時間に少しずつ進めることも可能です。
STEP 21秒で判断!「1軍・2軍・引退」の高速仕分け術
今シーズン着た服を手に取ったら、深く考え込まず、直感で3つに仕分けていきます。
問いかける質問は、ただ一つ。「来シーズン、これを心からときめいて着たいか?」
1軍(スタメン):
「絶対に着る!大好き!」と即答できる服。来シーズンのスタメンとして、最高の状態で保管します。
2軍(ベンチ):
「うーん、迷う…」「痩せたら着るかも」と、少しでも迷いが生じた服。一旦「保留」として、別のケースに保管します。
引退:
「今シーズン一度も着なかった」「もうときめかない」と判断した服。「ありがとう」と感謝して、手放すことを検討します。
この「2軍(ベンチ)」という選択肢があるだけで、「捨てなきゃ」というプレッシャーから解放され、仕分けのスピードが格段にアップします。
STEP 3「しまう前のケア」は“ついで”で済ませる
「衣替えのために、まとめて洗濯する」と考えると一大作業になります。
そうではなく、シーズン終わりの数回の洗濯の際に、「これは、このまましまう服だな」と意識して、いつもより丁寧にケアするだけでOKです。
- ニットやおしゃれ着は、おしゃれ着洗剤で優しく洗う。
- 天気の良い日に、カラッと完全に乾かす。
- 家で洗えないコート類だけをクリーニングに出す。
このように「ついで」に済ませておくことで、衣替え当日の負担を大幅に減らすことができます。
STEP 4来シーズンが楽しみに!プロ仕様の収納テクニック
仕分けた「1軍」と「2軍」の服を、最高の状態で保管するためのテクニックです。
- 防虫剤は「上」に置く:防虫剤の成分は空気より重く、上から下へ広がります。収納ケースの底ではなく、服の上に置くのが正解です。
- 湿気対策も忘れずに:収納ケースの四隅にシートタイプの除湿剤を置いたり、衣類の一番下に新聞紙を一枚敷いたりするだけでも効果があります。
- 収納場所は「天袋よりクローゼット下段」:湿気は下に溜まり、熱は上にこもります。温度変化が少ないクローゼットの中段や下段が、実は衣類の保管に適しています。
STEP 5来シーズンの服を出すときは「1軍候補」だけ
さあ、いよいよオフシーズンの服の出番です。
ここでも「全部出し」はしません。
まずは、前のシーズンに「1軍」として保管した服だけを、クローゼットに出しましょう。そして、「2軍」として保管していたケースは、すぐには開けません。
まずは1軍の服だけで1ヶ月ほど過ごしてみて、「やっぱり、あのカーディガンがないと不便だな」と感じたものがあれば、その時に初めて2軍のケースから取り出すのです。
意外と、2軍のケースを開けることなく、シーズンが終わることも多いですよ。
普段からできる「プチ衣替え」で、もっと楽になろう
年に2回の一大イベントにしないために、普段からできる簡単な習慣をご紹介します。
習慣1:クローゼット内に「迷い箱」を作る
シーズン中に「この服、なんだかもう似合わないかも…」と感じた瞬間に、ポイっと入れておく「迷い箱」を用意します。
衣替えの時は、まずこの箱の中身から手放すだけで、仕分けの一部が完了します。
習慣2:服を買うときに「オフシーズンの居場所」まで考える
新しい服を買うときに、「素敵!」という気持ちだけでなく、「着ない時期は、どこにしまおう?」と、保管場所までイメージするクセをつけましょう。
収納場所がなければ、何かを手放すか、購入を諦める、という冷静な判断ができるようになります。
習慣3:ハンガーの色や向きで「着た・着ていない」を管理する
シーズン始めに、クローゼットのハンガーを全て同じ向きに揃えておきます。
そして、一度着た服は、ハンガーを逆向きにして戻すだけ。シーズン終わりには、向きが変わっていないハンガーの服が「一度も着なかった服」だと一目瞭然になります。
まとめ:衣替えは、新しい季節の自分に出会うための“準備運動”

衣替えは、単に服を入れ替えるだけの面倒な作業ではありません。
それは、ワンシーズンを共にした服に感謝し、次の季節をどんな自分で迎えたいかを考える、大切な自分との対話の時間です。
「この元気な色のスカートを履いて、新しい場所に出かけてみよう」
そんな風に、次の季節への期待感を高めるための、楽しい“準備運動”だと捉えてみませんか?
まずはクローゼットから、今シーズン一番お世話になった一着を手に取り、「今シーズンもありがとう」と伝えてみてください。
きっと、憂鬱だった衣替えが、少しだけ愛おしい時間に変わるはずです。